中金堂

中金堂も興福寺の見どころ。
創建より6回の焼失・再建を繰り返し(7回とも)、平成30年2018年に再建された金堂。
興福寺には中金堂の他に東金堂と西金堂の3つの金堂があったが、中金堂は興福寺の伽藍の中でも最も重要な建物だった。

江戸時代の享保2年1717年に焼失した後は財政難で再建が進まず、百年後に町屋の寄進により仮のお堂が造られたが規模が小さく、2000年に解体され2018年に本来の大きさで再建された。
あくまで仮設としての建立で長期使用を想定しておらず、材木に不向きなマツが使われたため、急速に老朽化が進み平成に解体された。
※建築材にマツが使われるようになったのは室町時代。
奈良はほとんどヒノキだったが採れなくなり、平安時代になるとスギ、鎌倉はケヤキ、室町はマツも使われるようになっていく。
中世に強大だった興福寺も江戸時代になるとかつての勢いもなく、以前のように焼失する度に堂宇を復興させるだけの経済力はなかった。
寺領は他の寺院と比べて破格とも言える2万石余りが認められ、体裁は保ったが、奈良奉行が置かれ幕府の監視を受け、幕府の財政が悪化すると伽藍の復興資金を得られなくなり、その結果、中金堂を仮に造るにとどまった。
昔は中門があり金堂と繋がっていた。
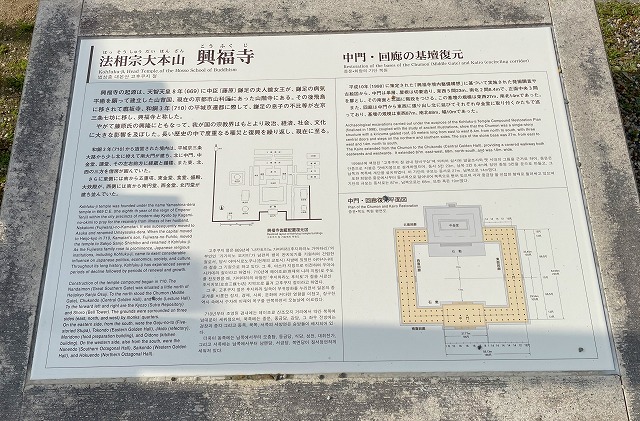

中金堂は約60億円の再建費がかかっていて、カメルーン産のケヤキが使われている。
このカメルーン産ケヤキというのが個人的には面白いと思う。
日本の寺院の木材は檜が最も適しているが、現在国内に使える檜はない。
以前は台湾産檜に頼っていたが、現在輸出が禁止されており、寺院の再建改修は檜以外の木材に頼らざるを得ないのが現状。
興福寺では熟考の末に柱にカメルーン産のケヤキを使うことにした。
一気に買うと原木が高騰するため7年かけて二つの会社で少しずつ買ったという。
カメルーンでは当時既に原木の輸出が禁止されていたが、禁止になる前に伐採された木は輸入でき、辛うじて手に入れることができた。
『蘇る天平の夢 興福寺中金堂再建まで。25年の歩み』より
横木にはカナダのヒバが使われている。
ケヤキは縦に使うなら、つまり柱として使うには優れているが、横木には適していないらしい。
ついでに寺院建築の木材はカナダのものも日本の風土と合っているが、中金堂の再建時は適した大きさの木がなかったらしい。
寺院の再建改修に必要な木材は現在、世界中を探しても不足している。
そのうちアルミで造るようになる、なんてことも言われている。
現に中国ではアルミで塔を造っているらしい。

中金堂がそうした木材不足を解決して再建したと思うと、ゆっくりと見入ってしまう。
瓦は約7万枚の瓦を3年の歳月と延べ9000人の瓦職人の手で作られた。
瓦は焼く前の乾燥が難しい。
水分が残っていると膨張して割れてしまうので、ゆっくり均一に乾かすには手間と経験が必要。

中金堂の拝観料は500円。
中はさほど広くなく、復原された建物の中に江戸時代に復元された本尊が祀られている。
その近くにある4体の仏像は奈良時代だったから、昔のもの。

何気なく観るなら数分で拝観が終わってしまい、500円は高いと思う。
が、以前なら間違いなくそう思っていたが、カメルーン産のケヤキが使われていることを意識して堂内の柱を観ると、なかなか面白い。

阿修羅像が展示されている国宝館のパネルで知ったが、中金堂は平城宮の第一次大極殿と同じ規模とのこと。
天皇が仕事をされる、国家の一大事業を行う平城宮の第一次大極殿と同じ規模なのだ。
そこと同じ大きさのものを造ってしまうあたりも、それだけ奈良時代に藤原氏が大きな力を持っていたことが分かりお面白い。
平城宮跡歴史公園の復元された第一次大極殿からは興福寺の堂塔が見える。
興福寺から天皇のお住まい、政治の場を見下ろす場所に興福寺があるのも、藤原氏の強さがうかがえる。
補足として、第一次大極殿の建物自体は当時は基盤がもっと高かったから、目線上は興福寺よりも高かったのもしれない。
中金堂の前には南大門跡がある。
かつては南大門の左右に境内を囲む塀があった。
他の奈良の古寺と同様、興福寺も南門があり、そこが正門だった。
なので、きちんと参拝したかったら猿沢池のある南から参拝するのがお勧め。

南円堂

中金堂の西にあるのが南円堂。
その北はかつては西金堂があり跡地に基壇・礎石が残されている。
先述の通り興福寺にはかつて3つの金堂があった。
西金堂には阿修羅像が八部衆像の一体として祀られていた。
南円堂は藤原冬嗣が父 内麻呂の追善のために建立したお堂。
現在の建物はこれまで4度再建されたもので、江戸時代の寛政元年(1789)に再建されたもの。
※藤原冬嗣:弘仁元年(810年)の薬子の変で式家の勢力が衰えると嵯峨天皇の信任を得て急速に台頭。
これにより北家が栄え他家を圧倒するようになる
八角形のお堂は日本では個人を追悼する意味があり、また記念堂に使われる。
北円堂

その先にあるのが北円堂。
興福寺を造った藤原不比等を弔うために建てられたお堂で、現在の建物は平重衡の南都焼討で焼失した後、鎌倉時代の承元4年(1210年)頃に再建された建物。
この後に紹介する三重塔とともに興福寺最古の建物。
軒の隅には三手先斗栱(五重塔で説明)が使われており、創建当初の姿を残している。
外からは分からないが大仏様も使われている。
『奈良の寺々 古建築の見かた』より
日本に現存する八角円堂のうち、最も美しいと賞賛されている建物。
興福寺の境内の西の端のこの地は、かつて平城京を一望できる一等地。
興福寺から西を見れば平城京の中心が見渡せ、また平城京の中心部からは春日山を背景に興福寺の堂塔がひときわ目を引いた。
名作として知られる木造無著・世親立像(むじゃく・せしんりゅうぞう)が安置されていて、春・秋の一定期間に公開される。
鎌倉時代の国宝。
木心乾漆四天王立像(北円堂所在)(してんのうりゅうぞう)
平安時代・国宝
三重塔

北円堂の前の坂を下りると(南に進むと)三重塔がある。
治承4年(1180年)の平重衡による南都焼討で焼失してから間もなく再建されたもので、北円堂と共に興福寺で最古の建物。
平安時代の建築様式を伝えています
同時期に焼かれ再建された、東大寺の南大門と比較すると面白い。
東大寺の南大門が大仏様を用いて、コスパ重視で短期間で一気に造ったのに比べて、興福寺の三重塔はしっかり時間をかけて、綺麗に再建している。

藤原氏の氏寺だった興福寺は自力で再建するだけの経済基盤があった。
寄付や寄進で再建費を募り、また各地の荘園に税をかけて資金を集め、お金をかけて豪華に造っている。
なので大仏様では決してない、整った華麗さのある荘厳さのある造りになっている。
間近で観ると木の茶色と壁の白色とのコントラストが何とも美しい。
平安時代らしさのある、木割が細く軽やかで、優美な線を醸し出していてる美しさがある。
五重塔の力強さとは違い、華やかさや優美さが全面的に押し出されており、その優雅な外観は平安時代の仏教建築の優れた一例とされている。
その一方で創建時の奈良時代の雰囲気も残している。
高さは約19m。
興福寺の建物は焼失の度に再建されたが、再建の際は天平への回帰が固く守られならがも以前よりも少し豪華にし、またその時代の流行を取り入れながら復興した。



コメント